
東京センチュリーは、経済産業省が発表する「DX銘柄」(2019年まで「攻めのIT経営銘柄」)に2015年から6年連続で選出されるなど、業界でもいち早くデジタルトランスフォーメーション(DX)の取り組みに力を入れてきた企業です。表面的なDXではなく、企業のビジネスを進化させ、新しい価値を生み出すようなDXを実現するためには何が必要なのでしょうか? IT推進部を統括するシステム部門長の筒井純二 執行役員にお話を伺いました。
「ロボットを管理するロボット」で飛躍的に業務効率を向上

―― 東京センチュリーは2015年から経済産業省が発表する「攻めのIT経営銘柄」「DX銘柄」に6年連続で選出されるなど、DXにおいては業界でも注目されています。こうした評価を得るに至った背景について教えてください。
どうすればサービス価値を高められるか、お客さまへいいものを届けられるか。とことん追求してきたからだと思います。
企業のDXにありがちなのが、目的と手段が逆になってしまうこと。DXをやることが目的化してしまうのではなく、企業の生産性やお客さまへの付加価値を飛躍的に向上させるために、デジタル化に取り組む。それが本来のDXのあり方であり、東京センチュリーはそこをぶらさずにDXに取り組んできました。
―― 具体的にはどのようなことを行なってきたのでしょうか。
大きく2つの方向性でDXに取り組んできました。1つ目がデジタルを使った「生産性向上」。2つ目は「既存ビジネスの変革」です。
1つ目の「生産性向上」の具体的な取り組みとして、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を活用した社内業務の効率化が挙げられます。これまで人が行ってきた入力業務などの単純作業をソフトウェアロボットに代替させることで、飛躍的な業務効率化に成功しました。

こうしたRPAの取り組みは、DXの代表的なものでもあるので、すでに導入している企業も多いかとは思います。しかし、RPAの効果的な運用を行うためには、ある大きな"課題"がありました。同じような課題に悩まされている企業も多いのでは、と推察します。
―― "課題"とは具体的にどのようなものでしょうか。
RPAで用いるロボットは、メーカーごとに特徴や作業の得意・不得意があるのです。社内業務のすべてを1社のロボットでまかなうのは現実的ではなく、さまざまなメーカーのロボットを適材適所で組み合わせて、複数導入する必要がありました。
そこで問題となるのが、複数の異なるメーカーのロボットをどのように管理するか。加えて、各ロボットが本当にコストに見合う成果を生み出しているのか、効果測定を行うことも重要でした。的確な効果測定ができなければ「適材適所のロボット運用ができているか?」などの判断もできないからです。
そこで私たちは「ロボットポータルサーバ」という、社内のロボットを一元管理する統合プラットフォームを自社の内製によって構築しました。いわば「ロボットを管理するロボット」を自分たちの手でつくったことが、大きなポイントとなりました。
これにより、さまざまなメーカーのロボットを効率的に一元管理し、的確な効果測定なども行いながら、年間約8,000時間、件数にして約90,000件もの作業を自動化することに成功しました。
「2025年の崖」を超えるため、高度なプロフェッショナル人材を結集

―― プラットフォームを自社で"内製"した点が興味深いポイントだと思います。なぜ、そのような自社での内製が可能だったのでしょうか。
私が東京センチュリーに入社したのは2016年ですが、そのときから将来を見据えた人材の育成・採用に注力してきました。
そこから数年がかりで、高度なスキルと専門性を持つIT人材の獲得に注力し、そうした人材が集う「IT推進部」を新設しました。AIやビッグデータの専門家、RPAのエンジニア、次期システムやインフラ基盤のスペシャリストなど、さまざまな分野のプロフェッショナルたちが集まった結果、自社での内製が可能になったといえます。
内製化が進むと、仕事のスピード感も変わります。外注の場合、外部の高度なスキルを持つエンジニアだとアポイントを取るだけに1週間以上かかることもあります。しかし、そうした人員が社内にいる場合、オンライン会議やチャットで即座に要望を伝えられます。こうしたスピード感の違いも、自社で内製する大きなメリットです。
―― 日本では自社のシステムでも、外部のベンダーなどに委託するケースが一般的ですよね。
その点がDXを行う上での大きな課題となっているのです。
例えばアメリカ企業では自社でエンジニアを抱えている会社も多いですが、日本は外部のベンダーやIT企業に外注するケースの方が多い。これは日本独自の効率化の結果だとも言えますが、ことDXにおいてはこれが裏目に出ています。例を挙げるなら、外部の人材に頼りすぎた結果、社内の人間ですら自社のシステムについて理解できていない"ブラックボックス化"。こうしたことがDXの大きな障壁になっています。
私はこのような日本のシステム投資のあり方、考え方を変える必要があると思います。経済産業省のレポートによると、日本企業のDXがうまく進まなければ、2025年からの5年間で最大12兆円の経済損失が出るとも予測されています。いわゆる「2025年の崖」と呼ばれる問題です。
私たちはこうした事態を見越して、早々からゲームチェンジを図るべく、数年がかりで内製化を進めてきました。そしてこの取り組みは、社内業務だけでなく対外ビジネスにも関わっています。それが、冒頭で話したDXの2つ目「既存ビジネスの変革」です。
"内製化"できる強みを対外ビジネスにも活かしていく
―― 「既存ビジネスの変革」とは、具体的にどのようなものでしょうか。
具体例を挙げると、シンガポールにおける「オートローンのWeb申込・自動回答システム」の導入があります。
シンガポールでは、日本でいうマイナンバーのような国民の個人情報が保存された「My Info(マイインフォ)」という国が提供するデータ基盤があります。ここには名前、生年月日、国籍、勤務先、年収などの個人データが記録されています。このMy Infoと連携し、お客さまがローン審査を行う際、PINコードを入力すると、個人データが当社に送られて即時審査が行われるような仕組みを構築しました。これにより、お客さまは24時間365日いつでもローンを申し込めるようになりました。
今後、他の国でも同様の取り組みが可能になるかもしれませんし、日本においても、マイナンバー制度の運用次第では、こうしたサービスを構築できるかもしれません。そのときは、ここで培ったノウハウを大いに役立てたいと思っています。
―― 社内業務だけでなく、対外ビジネスもDXで進化させているのですね。
効率化や自動化、使いやすさの向上やトラブルの減少......社内業務も対外ビジネスも、根底にあるニーズは一緒です。つまり社内業務のような「非競争領域」のDXは、「競争領域」である対外ビジネスにもつながっていくのです。だからこそ、内製できるチームを社内に持つ企業が、対外ビジネスにおいても有利になっていく。
例えば、東京センチュリーの事業に密接な自動車分野では今、急速にデジタル化が進んでいます。今後、ライドシェアや自動運転などのさらなる発達も予想され、私たちの既存業務もどう変化するか、先が読みづらい時代が訪れています。未来の変化をいち早く予測し、スピーディにお客さまの求める新サービスを実現するためには、速度と小回りのきく内製のメリットを大いに生かしていくことがカギとなるでしょう。

失敗を恐れない姿勢が「攻めのDX」には重要
―― DX領域で東京センチュリーがこれから取り組んでいきたいことを教えてください。
今、特に力を入れて取り組んでいるのが「新規ビジネスの創出」です。
DXのメリットは、エンドユーザーの声や要望を、サービスやお客さまとのタッチポイントにダイレクトに反映できること。最新のデジタル技術を駆使して、お客さまの声をサービスに取り込み、本当に求められるサービスをつくっていきたいと考えています。GAFAのような巨大企業も、それをやることで大きな成功を収めています。
たとえばレンタカー事業では、お客さまアンケートの分析を行っていますが、ロボットやAIがデータ分析すれば、人間よりもずっと多くの声を反映できます。人間なら数人がかりで1週間かかる分析でも、AIなら1時間足らずで終えてしまうかもしれない。そういったデータ分析のあり方が可能になれば、新規ビジネスの創出にも必ず結びつくはずですし、将来的には、そこで培ったノウハウを社会にも還元していきたいと考えています。
逆に言うと、今の時代にお客さまの声を速やかにサービスに反映できない企業は、大きく後れを取ることも意味します。とりわけ変化の多い自動車業界では、お客さまのニーズを汲み取って新サービスを生み出すことがこれからさらに求められてくるはず。だからこそ社内でデータを分析し、活用できる体制が必須なのであり、ここでも"内製可能"という強みが活きてくるのです。
東京センチュリーのIT推進部は、今までIT部門が担っていた社内インフラの保守業務だけでなく、対外ビジネスの未来をも創っていく存在です。いわば企業の「生命線」的な存在から「最前線」を担う存在へと進化しているのです。

―― 日本のDXでは、社内業務やシステムの保守という「守りのDX」が多いと言われます。新しいビジネスや価値を生み出すような「攻めのDX」を行うポイントはどこにあるでしょうか。
「守り」だけでは、企業の成長には決してつながりません。以前、シリコンバレーの世界的企業を訪問したとき、社内の食堂に「Fail Fast(早めに失敗しろ)」という張り紙が掲げられていたのを覚えています。とても印象的でした。
つまり、彼らにとって失敗とは避けるべきものでも、恐れるものでもない。むしろ褒められるべきものなのです。日本企業はとにかく失敗を恐れてチャレンジを避けたり、失敗を隠したり、取り繕ったりする傾向が強い気がします。それでは到底"攻め"の姿勢には転じられませんし、小さな失敗を恐れたことが、結果的に大きな失敗へとつながってしまう。
失敗を恐れずに攻めること。そのために、新しい技術を貪欲に取り込んでいくこと。こうした企業文化を醸成することが、攻めのDX、ひいては新しいビジネスの創出につながっていくのだと私は思います。
※記事の内容、肩書などは掲載当時のものです
おすすめ記事
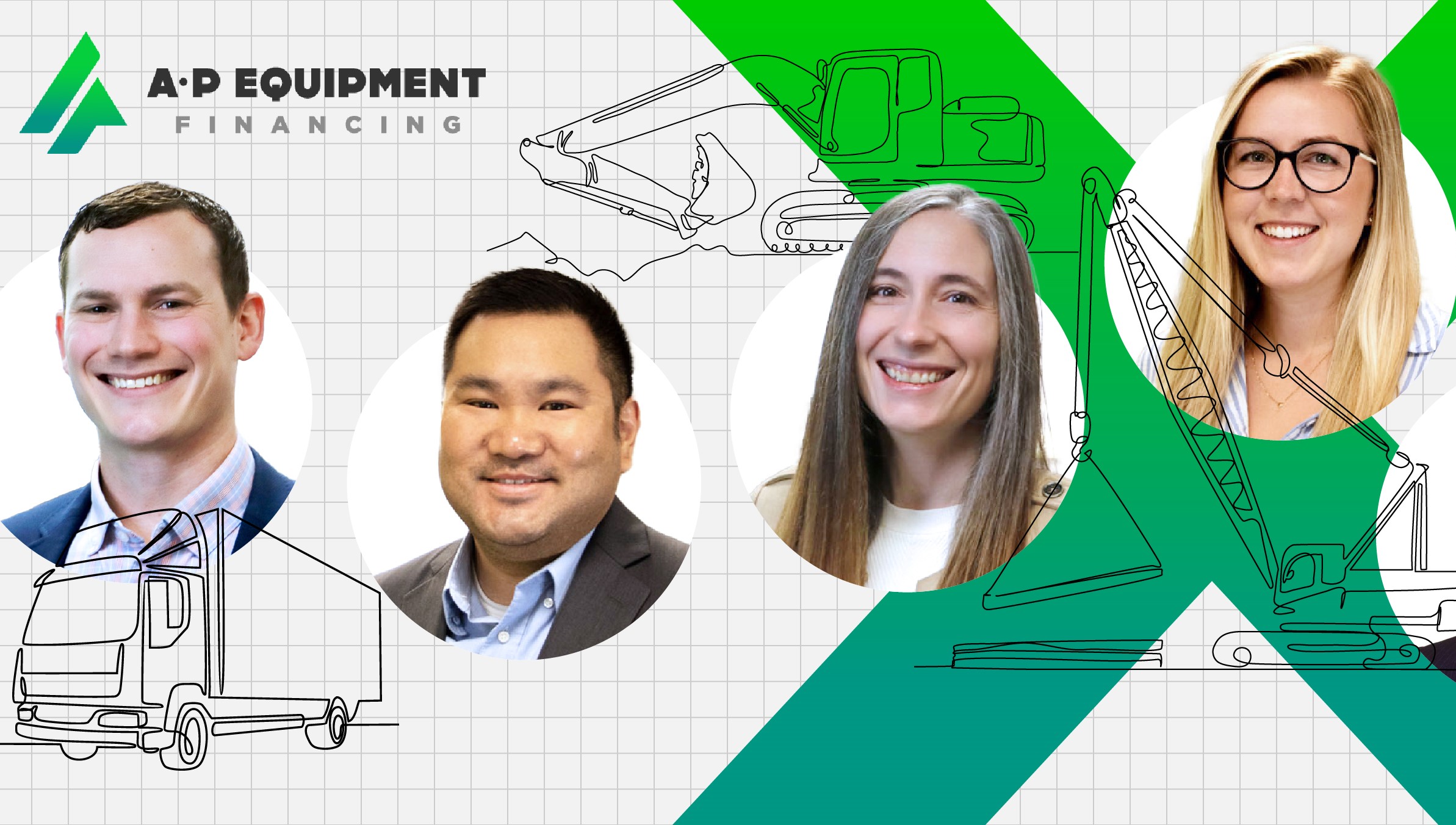
2024年3月29日
近年、私たちの⽣活や働き⽅のあらゆる⾯で…

━トップに聞く、「変化を創造する」攻めのDXとは?━
2023年11月22日
「自らを変革し、変化を創造する」私たち東…




